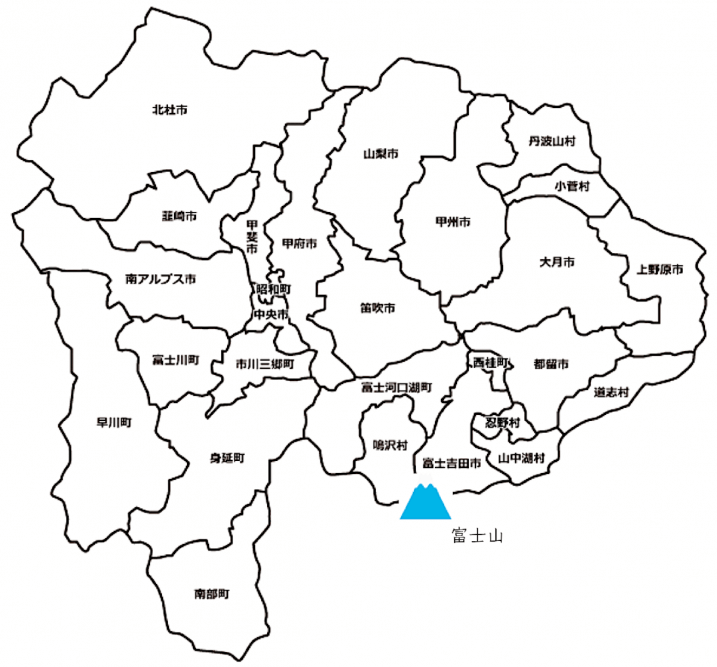志村ふくみ『一色一生』大活字本シリーズ / 感想

最近、志村ふくみさんの『一色一生』という本を読みました。新しいものと入れ替えだったようで、図書館で配布していた大活字本シリーズです。大活字本シリーズとは、その名の通り大きな字で書かれ、普通の本とは違う装丁になっています。
老眼がひどくなってきたので老眼鏡は欠かせませんが、スマホの字体も太字、さらに大きな文字で最大限に設定しているので、家族が見ると大抵ぎょっとした声をあげます。
さて、結構な老眼の私にとっても老眼鏡なしで読めるように作られたのが、この「大活字本シリーズ」。その存在を今回初めて知ったのですが、同じように初めて読むのが、志村ふくみさんの本です。
志村ふくみさんは、1924年生まれ、染織家、紬織の重要無形文化財保持者(人間国宝)であり、随筆家でもあります。この本は、志村さんが58歳のとき最初に著した本で、出版を強く推した評論家の大岡信さんが序文を書いています。
私にとって染織とは未知の世界で、近寄りがたい崇高な世界なのかなと思っていましたが、この本を読み、日本人が昔から積み重ねてきた日々の暮らしや、四季折々の自然と決してかけ離れたものでないことを知りました。
また一方、自然と謙虚に向き合い、自然から繊細な色を生み出し続けてきた志村さんをして「かつて一色に十年と思っていたが、この頃は一色一生と思っている。」といわしめた染織の世界の奥深さをも知ることができました。

本のなかに出てくる色の名前は、今まで私が耳にしたことのない名前ばかり。かめのぞき、縹(はなだ)、路考茶(ろこうちゃ)など一体どんな色なのだろうと調べてみると、ちゃんと辞書にも載っていて、決して染織の世界だけの特別用語ではありませんでした。
日本には四十八茶百鼠あるといわれるほど、同じ茶色や鼠色でも微妙に違いがあり、日本人はそれらを見分ける鋭い眼力をもっているそうです。
その色の違いを志村さんはとても美しい日本語で識別されています。
例えば、「たそがれに白々と咲く夕顔に翳の射す情景」とか「白い磁器の茶呑碗にほんのすこし呑みのこされた煎茶の夕やみに浮かぶ色」とかいうようないいかたで表現されるのです。
色見本で確認すると、確かに少しずつ色が違うのはわかるのですが、その微妙な色の加減はとても言葉で正確に表すことはできません。美しい色を生み出す人は、美しい日本語も紡ぎ出すのだと思いました。
この本には、染織の話だけでなく、のちに人間国宝にまでなる志村さんの劇的な半生も綴られています。
意外なことに芸術家としての出発は、幼い二人の子どもを抱え生活のためだったとのこと。
かつて織物に情熱を傾けながら、中途で断念したお母様のあと推しがあったとはいえ、初めは工芸の先生に、子どもを抱えながら片手間にできる仕事ではないと、厳しくいさめられたそうです。
しかし、別の先生に「私はあなたに織物をすすめることもやめさせることも出来ない。ただ、もしこの道しかないとあなたが思うなら、おやりなさい」といわれた言葉に導かれて迷うことなく歩んできたと語られています。
人生の岐路に立ったとき、どう道を選択していくか、非常に示唆に富んだ話だと思いました。
志村さんは、58才で随筆を書き始め、95才の現在もなお現役の染織家として着物を作り続けています。生き方そのものに『一色一生』が著されているような気がして、大変感銘を受けました。
以下は、印象的だった志村さんの言葉です。
植物には全て周期があって、機を逸すれば色は出ないのです。たとえ色は出ても、精ではないのです。花と共に精気は飛び去ってしまい、あざやかな真紅や紫、黄金色の花も、花そのものでは染まりません。
友人が桜の花弁ばかり集めて染めてみたそうですが、それは灰色がかったうす緑だったそうです。幹で染めた色が桜色で、花弁で染めた色がうす緑ということは、自然の周期をあらかじめ伝える暗示にとんだ色のように思います。
このように色の法則の追究は、長い年月かけて醸成された高度な日本の文化の特色で、湿潤の、四季の推移の日本にのみ生まれた色彩だと思います。
自然界の変幻極まりない仕組の中には、一定のリズムや周期がめぐってきて、われわれにほんの一滴のしずくをしたたらせてくれるのです。それを受けとめる態勢がこちら側に整ったとき、はじめて色が生まれるのです。
大切なことは、その色の一つ一つが純一に自分の色を奏でていることだ。色にも音階(色階というべきかも知れないが)があって、ドとミの間にどれほどの微妙な音色があるだろうか。日本人は古来、どれほどの微妙な色階の判別をなし得ただろう。しかも不可思議ともいえる色名を創造した。
出典:志村ふくみ『一色一生』より